プロローグ ― 泡の海を渡る者たち
宇宙は空虚ではない。無限の真空に見える闇の奥には、量子の揺らぎが泡のように生まれては消え、時空をさざめかせている。人類がそれを「真空泡」と呼ぶようになったのは、単なる比喩ではなかった。重力波望遠鏡と超光速理論の進展によって、我々の宇宙そのものが「泡の網目」によって縫い合わされていることが分かってきたのだ。
二十二世紀半ば、探査艦《アステリオン》のクルーは、その泡を利用して初の星間航行に挑もうとしていた。彼らの目的はただの航海ではない。人類文明を次の段階へと押し上げる「泡の道」を切り拓くこと。そこには未知の物理法則と、そして人類自身の精神的な試練が待ち受けていた。
第一章 ― 泡の門
航宙士アヤ・キサラギは観測窓の向こうに揺らぐ光を見ていた。通常の宇宙空間では存在しない、淡い虹色のゆらめき。真空泡の境界が視覚化されたものだった。
「航路計算、完了しました」
と副長のリー・ツァオが報告する。
「推進炉を臨界へ。全員、耐圧姿勢」
アステリオンの船体を包むシールドが強化され、空間そのものがきしむような振動を発する。次の瞬間、艦は光のトンネルに吸い込まれた。
それはワープでもなければ単純な亜空間航法でもない。泡と泡の境界をすり抜けることで、宇宙の網目をショートカットする――「泡航法」。
乗組員たちは数秒間、上下も前後も失ったかのような浮遊感に包まれた。
アヤは息を呑み、心の中でつぶやいた。
「私たちは、本当に泡の中を漂っている……」
第二章 ― 泡の内部
航海記録には、最初の泡内通過の光景が詳細に残された。
泡の内部はただの空虚ではなかった。光は歪み、無数の鏡面が互いを映し合うようにきらめく。まるで万華鏡の中に艦が迷い込んだようだ。時間感覚も曖昧になり、時計の針が早送りと巻き戻しを繰り返す。
船医のモリナ博士が驚きの声を上げた。
「クルー全員の脳波に干渉が起きています。夢を見ているときと同じ状態だ」
アヤの意識にも奇妙な映像が流れ込んできた。子供のころに遊んだ川辺、亡き父の笑顔、そしてまだ見ぬ未来の都市の姿――。
「これは……泡が人の記憶を映している?」
モリナは答える。
「あるいは、我々自身が泡の揺らぎを解釈しているのかもしれない」
科学と幻覚の境界が崩れる中、航海は続いた。
第三章 ― 泡の狩人
だが泡は静寂だけをもたらすわけではなかった。
センサーが異常な重力波を検知した。まるで何者かが泡の内部を意図的にかき乱しているように。
「接近物体、前方三万キロ!」
「船影……人類の設計とは思えません!」
視界に現れたのは、泡の光をまとった奇妙な艦影だった。曲線的な構造は自然物にも見え、表面は生き物の皮膚のように脈打っている。
「まさか、先住者……?」
誰かがつぶやく。
泡を利用するのは人類だけではなかった。宇宙にはすでに「泡の狩人」とでも呼ぶべき存在がいたのだ。
通信を試みるも、返答はなかった。代わりに相手は強力な波動を発し、アステリオンのシールドを震わせる。
「これは警告か、それとも――」
判断の余地はなかった。艦は緊急回避に移り、泡の別の層へと飛び込んでいった。
第四章 ― 泡の迷宮
そこからの航路は混迷を極めた。
泡は単なる抜け道ではなく、複雑に絡み合う迷宮だった。層を誤れば、同じ場所に戻されるか、あるいは未知の宇宙片へ放り出される。
アヤは操縦席で歯を食いしばりながら、感覚だけを頼りに舵を取る。
「ここは数字ではなく直感で読むしかない……」
リー副長が支援する。
「君の脳波を航法AIと同期させろ。人と機械、両方で泡を“感じる”んだ」
こうして人類は、科学と直感を融合させて泡を進む術を身につけていった。
数日後、ついに泡の出口が見えた。
第五章 ― 新たなる岸辺
光が爆ぜ、視界が晴れる。そこには見たこともない星系が広がっていた。巨大な青白い恒星の周囲を、リングを持つ惑星が巡っている。
「到達……成功だ」
歓声が上がる中、アヤはふと窓外を見た。泡の彼方で、あの奇妙な艦影が静かに漂っているのが見えた。敵意は感じられない。ただ、観察している。
「彼らもまた、泡の旅人……」
人類は孤独ではなかった。だが、それが友か敵かは、まだ分からない。
エピローグ ― 泡の向こうへ
《アステリオン》は帰還の途についた。航海は成功と呼ぶには危ういが、それでも新たな扉は開かれた。
報告にはこう記されている。
「我々は泡の中に旅した。そこは宇宙の裏側であり、人類の記憶の投影でもあった。未知の存在と遭遇し、宇宙の多様性を知った。――だが最も重要なのは、人間が直感と理性を融合させ、新たな航路を切り拓いたという事実である」
アヤは心に誓った。
「泡の道は、まだ始まったばかりだ」
そして彼女の視線の先には、数え切れない泡の連なりが、星々の海を越えて広がっていた。

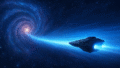

コメント