午後三時十七分の裂け目
霧のように薄く、しかし決して消えない光が空を裂いたのは、午後三時十七分だった。港湾都市ネオ・ヨコハマの湾岸線を走る高速軌道のすぐそば、冷房が効きすぎたカフェの窓に映る世界が一瞬だけ歪んだ。誰も驚かなかった。ここ数年、世界は「異常」に慣れてしまっていたからだ。しかし、あのときだけは誰の中にも、名前にできない違和感が走った。
「見たか?」と、窓際の若い研究者が声をひそめて呟いた。彼の名は黒川遥。タキオン理論の実戦応用チームに所属する若手で、世界のいくつかの研究所の共同プロジェクト《オルタス・ファイル》のために呼ばれていた。遥はポケットに収めた小さな端末をぎゅっと握りしめた。端末は、昨夜から断続的に拾っている微弱なスペクトルノイズを可視化している。ノイズの形は、まるで誰かが時間の端に針で引っ掻いたかのようだった。
タキオン──光速を越える仮想粒子。数学の式の中でしか生まれない虚数質量を持つ存在。現代の物理学はその実在性を否定しつづけてきた。だが、否定と無関係に、人々はタキオンという概念を使って夢を描いた。瞬間通信、未来予知、時間跳躍。どれも現実になるには致命的な問題を抱えている。因果律の破綻、観測者間で起きる時間順序の変化、理論の不安定性──それらを直視してきた者は少なかった。だが、プロジェクト・オルタスは違った。彼らは《可能性》を武器に変えようとしていた。
「データが確定値を示している」と、遥の顔に浮かぶ興奮は隠しようがなかった。彼は端末の波形を指差す。そこには、タキオンが理論上で示す特異点に酷似した痕跡が並んでいた。速度とエネルギーの関係──タキオンは光速に近づくほどエネルギーが無限大に発散するが、さらに速くなるとエネルギーは逆に下がり、速度が無限に近づけばエネルギーはゼロに近づく。遥はその式を、いつもノートの端に書き留めていた。式は冷たく、だが魅惑的だった。
「よし、観測点を増やす。今夜、港湾の北部と南部に分散配置を敷く。もし本当にタキオン的な現象が起きているなら、観測パターンは相対論的に歪むはずだ。――因果律が揺れ動く瞬間を捕まえる」
遥がそう決めると、窓の外の世界はまたいつもの灰色に戻った。人々は画面に映る好評番組に笑い、配達ドローンは約束どおりの時間に食事を運び、街は機械的に呼吸をつづけた。誰にも知られずに、しかし確かに、岸の下に不思議なものが流れている。
タキオンフラッシュの証明
三日後、観測網は「タキオンフラッシュ」と名付けられた現象を確定した。フラッシュは局所的に生じる時間軸の位相変化に似ていた。通常の観測器にとっては、対象が消えたか、瞬間的にすり抜けたように見えた。だが、専用の干渉計は波の位相に異常な進みを検出した。位相が進む、つまりある観測者にとっては出来事の順序が前後する可能性――それはタキオンのもたらす最も恐ろしい特徴のひとつだと、遥は考えていた。
事実、フラッシュに遭遇した複数の市民が互いに異なる記憶を持っていた。ある男は午前七時に出勤したと主張し、別の男は同じ通りで午前六時に銀行強盗があったと証言した。防犯カメラのログは矛盾していた。ログは分岐した時間の断片を映しており、どれもが「正しいように見える」。誰がそれを正すのか。誰が観測者の立場を決めるのか。法律も倫理も、まだその問いに答えを用意していなかった。
プロジェクトのメンバーは慎重だった。タキオンの理論は魅力的だが、実験的に扱うには危険が伴う。タキオン場理論は、真空の崩壊や対称性の破れの話に触れ、安定した物質世界を脅かす可能性を示唆していた。だが、資金提供者は違った。企業連合と国家は新たな技術競争の波にのまれ、誰よりも先に「先取り」したがっていた。タキオンを応用できれば、超光速通信が可能になるかもしれない。もし因果律の取り扱いを制御できるなら、情報戦で無敵になれる。そう考えたのだ。
遥のチームは二つの道を模索していた。ひとつは「観測と記録」に徹すること――タキオン的現象を安全にマッピングし、因果の歪みを特定する。もうひとつは、より危険で革命的な「制御」へと踏み出すこと。遥は後者を選んだ。理由は単純で、彼は「見たい」側の人間だった。理論数式が示す世界を、手触りのある現実へと押し出したいという一種の衝動が、彼を動かしていた。
制御プロトコル《庭》の起動
制御プロトコル第一号。コードネーム《庭》――それは小さな実験装置の名称でもあり、また遥の内面を表す言葉でもあった。《庭》は局所的にタキオン場を刺激し、位相を微量にずらすことで観測者間の時間的位相差を刻み、結果として「差分情報」を抜き出すことを企図していた。言葉で言えば抽象的だが、実装はシンプルな干渉計と位相制御モジュールの組合せだった。重要なのは位相の「幅」を超えないこと。位相を少しだけ動かし、世界を引っ掻くだけで済む。引っ掻きすぎれば穴が開く。誰もそれを望まない。
緊張のなか、遥は装置の起動コマンドを打ち込んだ。緩やかなハム音がする。空気がわずかに冷たく感じられ、装置内部のフィールドが立ち上がる感触が伝わってきた。最初の刺激は微弱で、測定器はそれに応じた。だが三回目のパルスが終わった瞬間、カフェの外の世界が再び歪んだ。これは偶然ではなかった。観測器はタキオンフラッシュに似た微小な位相乱れを拾ったが、それは制御されたものだった。
「データを流して。時間分解能を上げるんだ」――遥は声をかけた。チームメンバーの一人、白石芙蓉が冷静に応え、ログが膨大な波形を描き始めた。波形の中に、確かな“反復パターン”が現れた。繰り返し生じる小さな位相進行。正常な世界でなら見えない歪みの連鎖。それはまるで、時間の皮膚に雨垂れが落ちるようだった。
解析が進むにつれ、遥はあることに気づいた。位相の進行は情報を“先取り”するような形をとっている。小さな観測点から発生した刺激が、あたかも未来の状態を先に“触れる”ように、過去のログに痕跡を残すように見えた。これは、タキオンの持つ時間逆行性の一面が顔を覗かせているとしか思えなかった。
先取りされる未来と市場の波紋
最初に現れたのは小さな奇跡だった。街角の花屋が、翌朝に売り切れるはずのバラの束を午前中に回収したという報告。だが、その“奇跡”が次第に奇妙な連鎖を呼び、やがて社会の折り合いを狂わせ始めた。ある医師が「未来の記録」を元に診断し、予防的な処置を施して人命を救ったという話が広まると、保険会社が先物型の保険商品を売り始めた。市場は未来を先取りすることで利益を上げる術を見つけ、倫理は金銭に押しつぶされかける。
プロジェクト内部でも亀裂が生じた。倫理担当の古参研究者、浜口は言った。「我々がやっていることは、時間的独占の端緒だ。因果律を操作することは、人の自由と責任の概念を根底から覆す。望ましいわけがない」。だが、資金の大半を握る企業は態度を硬化させた。「可能性の独占は国家安全保障だ。競合が先に見つけたら我々は終わる」。浜口は黙殺され、やがて研究室を去った。
遥は疑念を抱いたが、同時にこうも思った。もし因果律に“亀裂”を入れられるなら、人類は病気を根絶し、災害を前もって回避できるかもしれない。それは人道にかなうのではないか。問題は『誰が未来を決めるのか』だ。遥は答えを出せないまま、装置のログを夜な夜な解析した。ログは次第に、あるパターンを示した。タキオンの位相進行の中に“固有モード”が存在するらしい。そのモードは、特定の位相周波数でのみ活性化する。そして、最も興味深いことにそれは「人間の観測意識のパターン」と位相的に共鳴するように見えた。
観測者の位相――芙蓉の仮説
芙蓉が最初に言い出した。彼女の声は静かだが確固としていた。「もし観測意識が位相に影響するなら、それを使う方法があるはずよ。≪観測を介した制御≫。つまり、我々が観測者として特定の位相を“選ぶ”ことで、出力される未来の枝分かれを選別できるかもしれない」
その考えは、理論的には破綻を含んでいた。観測問題は量子力学ですでに取り扱われているが、ここで触れているのは人間の知覚とマクロな位相変動が干渉するという仮説だ。多くの物理学者は鼻で笑うだろう。しかし芙蓉は物理学の本を閉じ、工学的に有効な実験をやろうと言った。彼女は自分の頭脳よりも手先の巧みさを信じていた。
実験が始まった。《庭》の次期バージョンは「観測環境」を操作可能にした。被験者に提示する映像や音声の位相を微妙に揺らし、その反応を観測する。観測者がどのように時間の「ずれ」を認知するか、そしてその認知がフィールドにフィードバックされるか検証するためだ。被験者は無作為に選ばれた市民たちで、同意は書面で得られた。遙は内心の不安を押し殺して、それでも実験を進めた。
最初のセッションで起きたのは、誰も予想しなかったことだった。被験者のひとり、名は梶原涼子。中年の女性で、幼い娘を亡くした過去を持つ彼女は、映像の中のわずかな位相ずれに反応して言葉にならない声をあげた。映像は単なる花の開花の再生だったが、涼子は「違う」と言った。「これは――昨日じゃない、もっと前。娘が笑っている」と。録画された生体反応は通常のパターンを超える位相の偏りを示していた。脳波において、特定の帯域の活動がタキオンフラッシュに同期したのだ。
芙蓉と遥は見つめ合った。もし人間の感性がタキオン位相に共鳴し、それが逆に場に影響を与えるのならば、我々は“観測によって未来を形づくる”可能性を持つ。恐怖と陶酔が同時に交錯した。
残滓の誕生と共同現実のほころび
ニュースが駆け巡る前に、彼らはもう一つの事実を知ることになる。《庭》はただ位相を刺激するだけの道具ではなかった。それは「選択の拡張」を生み出してしまったのだ。観測された人々の周囲では、ほんのわずかな確率で、選択されなかった枝(起こり得た未来)が“残滓”として実在するようになった。残滓は観測者が触れられない世界の記憶を保持し、干渉する。最初の残滓は小さかった。消えた駅のベンチ、違う服を着た通行人、過去の修正された領収書。だが残滓は増殖しやがて実質的な「情報差」を生んだ。誰かが選んだ未来の側面は強化され、それ以外は薄れていく。これは単純な確率の偏りではなかった。これは、意思決定が物理的現実の一部を抹消し、別の部分を強化することを意味していた。
浜口が戻ってきた。白髪が増え、目に疲労をたたえていた。「やめろ。これ以上は許されない。君たちは時間を“編集”している。永続的な記憶の齟齬が生じた世界で、人々の共同的現実認識が破綻する。法も契約も記録も、むしろ不安定になるだろう」と彼は怒鳴った。だがプロジェクトの主要スポンサーは動かなかった。彼らは残滓を金に替え、権力を拡げる方法を見出そうとしていた。
遥は分裂していく自分を感じた。彼は新しい知見に惹かれていたが、同時に責任の重さに耐えられなくなっていた。ある夜、彼はログを眺めながら一つの考えに襲われる。もし残滓が記憶を保持するのであれば、それは『別の世界の断片』と呼べるのではないか。すなわち、選ばれなかった可能性が現実の端に残り続けるとすれば、世界は層をなして重なっている――それを視覚化すれば、パラレルの薄膜が重なっているような姿を描けるかもしれない。
港に残る笑い声
ある晩、遥はひとり港へ出た。潮の匂いが混じり、冷たい風が彼の耳元を撫でた。そこに立つと、彼は自分が何をしているのかを理解したい一心で装置のテープを再生した。テープの端に残された最古のログは、かつて存在した小さな子どもの笑い声を繰り返していた。その笑いは、梶原涼子の娘のものに酷似していた。遥の胸を鋭く締めつけるものがあった。彼は装置の画面に映る波形を見つめながら、自分の手が震えているのを感じた。
「もし、選ばなかった世界が残るのなら、そこに行けるのか」――風が答えるはずもない。遥は自分が科学者でありながら、詩的な希望を抱いていることに気づいて笑った。だが彼の胸の奥底にある願いは真実だった。失ったものを取り戻すことはできない。だが別の“残滓”に触れることで、思い出の欠片を取り戻せるかもしれない。倫理的に許されるかは別として、人の心は時に理屈を超える行動を促す。
波形のなかの予感――目の開くとき
《庭》は拡張され、観測者の意識を組み込む第二期計画が承認された。実験は秘密裏に拡大され、非公開セッションが始まった。ある夜、遥は芙蓉と二人きりで制御室に残った。彼らの前には新型の位相スキャナーが鎮座している。スキャナーは残滓の“厚み”を可視化するように設計された。画面には幾層にも重なる微細なノイズの紋理が映る。そこには、梶原涼子の娘の笑顔だけでなく、見知らぬ景色の断片、まだ見ぬ未来の微かな構図が混じっていた。
「これが、君の望んだ答えか?」芙蓉が囁く。彼女の声には疲労と好奇心が混ざっていた。遥は答えを探して画面を見つめた。画面の奥で、波形の一つが鮮烈に跳ねた。瞬間、彼の視界は白く閃光に満たされ、記憶とも予感ともつかない映像が押し寄せた。梶原の笑顔、消えた駅のベンチ、そして――見知らぬ子どもが海辺で手を振る姿。その子どもは遥だった。
彼は激しいめまいを覚え、手すりにしがみついた。芙蓉が支え、彼女の表情は鋭く研ぎ澄まされていた。「データだ。これを見て。位相の位相、観測者の選択パターン、それに連鎖する残滓の周波数。これは――単なる局所現象ではない。何かが“秩序”を形成しようとしている」
画面の波形は次の瞬間、意味を持った音のように崩れ落ちた。遥の耳に入ってきたのは、一つの言葉だった。はっきりとした声ではない。だが彼の意識はそれを「来る」と解した。何が来るのか。彼の心拍は早まる。背後で廊下の電子ロックが一瞬だけ鳴り、誰かが近づいてくる足音がした。プロジェクトの管理者か、あるいは——。
遠くに、鋭い影が転がるような音がした。モニターに映る残滓の一部が、まるで生き物のようにうねり始めた。時間の薄膜が、ゆっくりとめくれあがる。そこに、確かに――何かがいる。
そして、画面の最も深いところに、一つの目が開いた。
(つづく)
参考・着想元
タキオンの性質、虚数質量やエネルギー–速度関係、因果律との関係などは、以下の解説ページの記述を元にSF的に執筆しました。詳しい基礎知識は参考にしてください。([SF空想のネタ帳][タキオンの基礎知識][タキオンのSF応用)

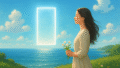

コメント