古の航海者たちに捧ぐ
古の航海者たちに捧ぐ
2178年。地球からおよそ50光時の彼方、探査船「アルタイル号」は無音の宇宙を漂っていた。
艦長のマリコは、操縦席に腰を沈め、前方に広がる恒星の海を見つめていた。
「星は嘘をつかない……昔の航海士たちはそう言った」
彼女は幼い頃、海洋民族ポリネシアの物語を読み、星を道しるべにした彼らの知恵に憧れた。
今、自分が指揮するこの船もまた、星を頼りに未知の航路を切り拓こうとしている。
視差という古い案に未来を託して
地球からの支援は、通信遅延とエネルギー不足によりもはや当てにならなかった。
この船が進むべき道を決めるのは、船自身の「目」――搭載されたカメラと望遠鏡だけだ。
航法主任イスカが言った。
「ニューホライズンズの小さな実験を覚えてる? 星の“視差”で位置を測るあれ。
あの時は精度が6,600万キロ程度だった。でも今は違う。改良を重ねれば、私たちも航路を描ける」
視差――遠くの星を背景にして、近い星の位置が微妙にずれて見える現象。
わずかな角度の違いを測定することで、船の現在位置を算出できる。
それは、地球の航海士が六分儀で太陽の高さを測ったのと同じ原理だった。
二つの星が導く道
だが、星は無限にある。どの星を基準にするかで誤差は大きく変わる。
イスカは画面に二つの星を映した。
「プロキシマ・ケンタウリと、ウルフ359。どちらも比較的近い。
遠い星を増やすより、この二つに集中した方が精度が出るはずだ」
マリコはうなずく。
「人間の目だって、片目より両目の方が距離感を掴めるものね」
やがて船のシステムは、この二つの星を“指標星”として登録した。
視差を刻むデータは、脈打つようにコンソールに流れ込む。
カメラに宿る六分儀
アルタイル号に搭載された望遠鏡カメラは、宇宙の六分儀と化していた。
船体の姿勢制御システムは、毎秒ごとに星々の揺らぎを観測し、位置を補正していく。
船員たちはそれを「星の呼吸」と呼んだ。
遠くの星が瞬き、近くの星がわずかにずれる――その呼吸を読み取ることが、命綱だった。
だが、観測精度を高めるためには望遠鏡の口径を拡大しなければならない。
補給も修理もない宇宙空間で、それは命がけの船外作業を意味した。
「私が行く」
マリコは静かに言った。艦長自ら星を測る六分儀を磨く。それが彼女の誇りだった。
遠く、近く、同時の旅
作業を終えたその夜、アルタイル号は未知の小惑星帯に突入した。
船体に無数の影が走り、船員たちの心に恐怖が広がる。
「航路が乱れてる!」
イスカの声に、マリコは目を閉じ、息を整えた。
「遠くを見て。近くも見て。両方を同時に」
指標星の視差を頼りに、船は針の穴を通すように進路を修正していく。
長い沈黙ののち、航路は安定した。船内に歓声が湧いた。
星々の六分儀は止まらない
数カ月後。船は新たな精度を達成していた。
誤差はついに0.01天文単位――約150万キロ。まだ不十分ではあるが、確かな進歩だった。
マリコは観測データを見つめ、かすかに笑った。
「星々は私たちを導いてくれる。私たちが見続ける限り、道は閉ざされない」
彼女は再び夜空に向けて、古の航海者と同じ言葉を心の中で唱えた。
「星は嘘をつかない」
アルタイル号は、静かに恒星間の闇を進んでいった。
「星は嘘をつかない……昔の航海士たちはそう言った」
彼女は幼い頃、海洋民族ポリネシアの物語を読み、星を道しるべにした彼らの知恵に憧れた。
今、自分が指揮するこの船もまた、星を頼りに未知の航路を切り拓こうとしている。
視差という古い案に未来を託して
地球からの支援は、通信遅延とエネルギー不足によりもはや当てにならなかった。
この船が進むべき道を決めるのは、船自身の「目」――搭載されたカメラと望遠鏡だけだ。
航法主任イスカが言った。
「ニューホライズンズの小さな実験を覚えてる? 星の“視差”で位置を測るあれ。
あの時は精度が6,600万キロ程度だった。でも今は違う。改良を重ねれば、私たちも航路を描ける」
視差――遠くの星を背景にして、近い星の位置が微妙にずれて見える現象。
わずかな角度の違いを測定することで、船の現在位置を算出できる。
それは、地球の航海士が六分儀で太陽の高さを測ったのと同じ原理だった。
二つの星が導く道
だが、星は無限にある。どの星を基準にするかで誤差は大きく変わる。
イスカは画面に二つの星を映した。
「プロキシマ・ケンタウリと、ウルフ359。どちらも比較的近い。
遠い星を増やすより、この二つに集中した方が精度が出るはずだ」
マリコはうなずく。
「人間の目だって、片目より両目の方が距離感を掴めるものね」
やがて船のシステムは、この二つの星を“指標星”として登録した。
視差を刻むデータは、脈打つようにコンソールに流れ込む。
カメラに宿る六分儀
アルタイル号に搭載された望遠鏡カメラは、宇宙の六分儀と化していた。
船体の姿勢制御システムは、毎秒ごとに星々の揺らぎを観測し、位置を補正していく。
船員たちはそれを「星の呼吸」と呼んだ。
遠くの星が瞬き、近くの星がわずかにずれる――その呼吸を読み取ることが、命綱だった。
だが、観測精度を高めるためには望遠鏡の口径を拡大しなければならない。
補給も修理もない宇宙空間で、それは命がけの船外作業を意味した。
「私が行く」
マリコは静かに言った。艦長自ら星を測る六分儀を磨く。それが彼女の誇りだった。
遠く、近く、同時の旅
作業を終えたその夜、アルタイル号は未知の小惑星帯に突入した。
船体に無数の影が走り、船員たちの心に恐怖が広がる。
「航路が乱れてる!」
イスカの声に、マリコは目を閉じ、息を整えた。
「遠くを見て。近くも見て。両方を同時に」
指標星の視差を頼りに、船は針の穴を通すように進路を修正していく。
長い沈黙ののち、航路は安定した。船内に歓声が湧いた。
星々の六分儀は止まらない
数カ月後。船は新たな精度を達成していた。
誤差はついに0.01天文単位――約150万キロ。まだ不十分ではあるが、確かな進歩だった。
マリコは観測データを見つめ、かすかに笑った。
「星々は私たちを導いてくれる。私たちが見続ける限り、道は閉ざされない」
彼女は再び夜空に向けて、古の航海者と同じ言葉を心の中で唱えた。
「星は嘘をつかない」
アルタイル号は、静かに恒星間の闇を進んでいった。
参考・着想元
本作は本作は「恒星間航行を可能にする具体的な技術」を基盤にワープドライブやナノテクシールドなど未来技術の発想を物語に組み込み、科学的考察とSF的想像力を融合させて執筆しました。


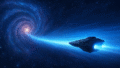
コメント